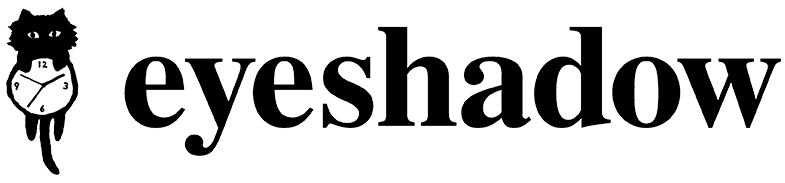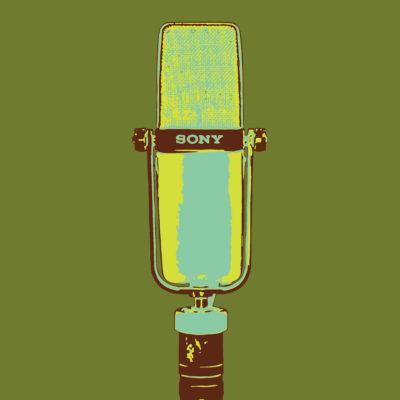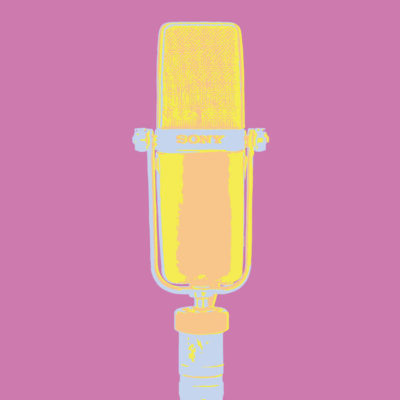ジャズとカヴァーの物語。
福田俊一
Ep.3 / 31 Oct. 2023
ジャズにおいてスタンダードとは、幾度も演奏されてきた曲・歌われた曲のこと。つまり、時代を超えてカヴァーされてきた名曲を意味しています。このサイトで筆者がペンを走らせるのは〈ジャズにおけるカヴァーにはどんなものがあるのか〉ということ。第3回目の記事となる今回は、スタンダードナンバーのひとつである「Somewhere in the Night」という楽曲を取り上げます。
この曲は、映画・テレビへの楽曲制作を多く手掛けたミュージシャン&アレンジャー、ビリー・メイが1960年に米国テレビ局ABCが放映したテレビ犯罪捜査ドラマ『裸の町(英題:Naked City)』のために作った1曲。インターネットの音楽データベースサイトで同曲について調べたところ、楽曲が制作された数年後、1963年ごろからジャズではカヴァーとしてレコーディングされはじめたようです。
私がこの曲に惹かれるのは、その美しくドラマティックなメロディー・ライン。さすが捜査ドラマのテーマソングだけあり、原曲はオーケストラによる壮大な演出がなされた華やかなアレンジ。しかし、「今宵もどこかで、私はあなたを探しつづける」というラヴソング的な歌詞もあり、ジャズではゆったりとしたメロウなアレンジが施されることが多いようです。アーマッド・ジャマル、エラ・フィッツジェラルドなど、同曲をカヴァーしたジャズ・ミュージシャンは数知れず。名演がいくつも残されました。
この曲を紹介するにあたり、ぜひ聴いてほしいカヴァー・ヴァージョンはこの3人。三者三様、それぞれ違った味と良さがあってジャズの楽しさがビリビリと伝わるはずですよ。
Cal Tjader カル・ジェイダー
カルン・ラドクリフ・ジェイダーJr.こと、カル・ジェイダーは米国カリフォルニア出身のヴィブラフォン奏者。50年代初頭にリーダー作を吹き込んだのを皮切りに、西海岸のレーベル《ファンタジー》を中心に続々と作品をリリース。時にピアノを、時にコンガなどパーカッションを演奏した彼はとても器用なミュージシャン。40年代半ば〜50年代はじめにあのデイヴ・ブルーベックのバンドでドラマーとしてレコーディングに参加したこともあります。ラテンのリズムとともに彼が繰り出すそのヴィブラフォンの音の揺らぎには、〈癒しと情熱〉という相反するアルファ波が共存。その【冷たい熱】もしくは【熱い冷静さ】という他のヴィブラフォン奏者にはない特異なサウンドを彼は表現しました。ジェイダーは非ラテン圏出身のミュージシャンとしては史上最も成功したラテン音楽ミュージシャンだとされます。ジャズファンに「1番 有名なヴィブラフォン奏者は?」と問えば、1位にはなかなか選ばれないような人なんですが、私のなかではミルト・ジャクソンやボビー・ハッチャーソンよりも特別な演奏者なんです。
そんなジェイダーも「Somewhere in the Night」をカバーしたひとり。《ヴァーヴ》から発表した65年作『Soul Sauce』に収録されています。ドナルド・バード(tp)やケニー・バレル(g)といった豪華ジャズマンも参加したピリ辛タバスコジャケの本作は、特濃ラテンリズム大盛りですが、「Somewhere〜」のようなゆったりレイドバックした美しい楽曲も魅力的。暑い夜の南米のビーチ、一組の恋人を眩しく照らす月灯り。寄せては返す波の向こう側で、ジェイダー奏でるヴィブラフォンの音色に呼応して星がきらめくよう。
想像力を豊かにさせるこの作品は、私が20代はじめのとある日、右も左もわからないままレコードを熱心に勉強していたころ、渋谷・宇田川町にあった今はなき小さな廃盤専門店で購入した1枚。教えられなければわからない雑居ビルの一室にその店はありました。DJをする店長が揃えたレアグルーヴ中心のラインナップのなか、どこか哀愁を感じさせる本作のアートワークが商品棚では異彩を放っていました。ジャケを手にしてピンときた訳ではないけど、そんな思い出補正も重なって、今となっては私の思い入れが詰まったアルバムに。いくつになってもずっと愛聴したいアルバムです。
Marlena Shaw マリーナ・ショウ
レアグルーヴ傑作として名高い『The Spice of Life』、《ブルーノート》から発表した75年作『Who Is This Bitch, Anyway?』が有名なジャズ・シンガー、マリーナ・ショウによるカヴァー。プロとしてのデビュー作、《カデット》からリリースされた『Out of Different Bags』にも「Somewhere〜」が収録されました。名アレンジャー、リチャード・エヴァンスがプロデュースを担当しています。彼が指揮するオーケストラもショウの力強い唄声をうまく引き立てています。
カデットにはエヴァンスがアレンジを施したファンキーな作品があります。例えば、ギタリスト=フィル・アップチャーチらが参加したエヴァンス率いるレーベルのハウス・バンド・グループ、ザ・ソウルフル・ストリングス名義のアルバムだとか。この頃(1960年代後半)はジャズがロックやソウル / ファンクの要素を取り込むようになった転換期。ジャズが歩みだした新たな方向性は当時の人たちにとってはさぞかし新鮮だったでしょう。ショウの本作も例外ではなく、ソウル的な歌唱でありながら心揺さぶるアレンジも相まって大変よきテイクに。流麗なバラード風の演奏だった先述のカル・ジェイダーのそれとはまた趣きが異なり、ほろ苦いブルースがフワッと口の中に少し残るちょっとおセンチで素晴らしい演奏。短いが印象的なソロを吹くフルート奏者が誰なのか気になり、レコードのジャケ裏を見ましたがクレジットが載っておらず。なんてこった。クールなカッティングをキメるギタリスト=これはアップチャーチか? この1枚、レコードでは当時北米で3回ほど再発されましたが、80年代になって日本盤でも発売されています。世界で唯一CD化がなされたのも我が国だというのは、同じ日本人ジャズファンとして誇らしい。日本人は耳が肥えた民族であり、いかにジャズを愛しているかがわかります。
Jack McDuff ジャック・マクダフ
ブラザー・ジャック・マクダフは1960年から活躍したオルガン奏者。リーダー作をいくつも発表したほか、サイドマンとしても数多くの著名ミュージシャンの作品に参加。今も昔もオルガンが好きなジャズファンから高い評価を受ける優れたプレーヤーです。彼の魅力は高速で展開される打鍵の連続がアツい、スロウなバラードでも聴かせる、ソロで聴くものを惹きつける、などなど。ジャズオルガンの先駆者ジミー・スミスともまた違うイケイケな感じがとても◎なアーティストです。私も大好き、というかもはや愛してる。好きすぎて辛いわ。
マクダフも63年に西海岸サンフランシスコのクラブ「ジャズ・ワークショップ」でのライブで「Somewhere〜」をカヴァー。3大ジャズレーベルと呼ばれる《プレスティッジ》からの作品『Live!』に収録されました。同曲を演奏するメンツは彼のほか、若き日のジョージ・ベンソン(g)、そしてジャズファンク界隈でも有名なジョー・デューク(ds)という3人。トータル4分弱の演奏のうち、たった50秒ほどですがマクダフが至高のソロを披露します。ハイトーンで奏でられるオルガンの音色が耳に心地よく、その抒情的で哀愁漂うフレージングには惚れ惚れとするほど。曲自体は落ち着いたテンポで、デュークがカンカンと叩くカウベル、上下するハイハットの音がリズミカル。ベンソンのバッキングもリラックスしていて、いやぁ〜、いい仕事してますね。まるで夢見心地のような時間。
彼の素晴らしさをうまく言葉で伝えられないのが私としてはもどかしいのですが、かんたんにいうなら〈熱〉と言い表したいです。マクダフがオルガンに宿す熱はジャズにおいても独特で唯一無二。荒々しく激しいハードバップの演奏をするときも最高だし、絶品バラードを奏でるときも最高。ライブ盤ならではの空気感や観客の拍手も加わって何もかもが最高。マクダフ味がバッチリ効いた「Somewhere in the Night」、ぜひ聴いてみてください。
(つづく)
- Profile
- 福田俊一(ふくだ・しゅんいち)。1984年、東京都大田区生まれ。レコードコレクターであり、中古レコード店スタッフ。武蔵大学人文学部欧米文化学科卒。大学1年生のとき、体育の授業でラジカセから流れていたL L・クール・Jのラップに心奪われ、ヒップホップ/R&Bに熱中になる。そののち、サンプリングに魅了され、徐々にソウル/ファンクやレアグルーヴにも興味を持つように。大学を卒業すると、レコード収集にハマる。ネタ系を掘り下げるようになった最終結果、次第にジャズに惹かれるようになり、30代前半のときにモダンジャズ最高峰レーベル、《ブルーノート》のほぼ全てのレコードをオリジナルでコンプリートした。
Instagram
Our Covers


Iñigo Pastor

奥山一浩

TOMOE INOUE
EyeTube
![Kacey Musgraves – Rainbow Connection [Kermit the Frog]](https://eyeshadow.jp/commons/images/uploads/2024/05/kacey-musgraves_rainbow-connection-712x400.png)
Kacey Musgraves – Rainbow Connection [Kermit the Frog]
![フジコ・ヘミング – 月の光 [ドビュッシー]](https://eyeshadow.jp/commons/images/uploads/2024/05/fuzjko-hemming_claire-du-lune-712x400.png)
フジコ・ヘミング – 月の光 [ドビュッシー]
![Larry Graham and Graham Central Station – Higher Ground [Stevie Wonder]](https://eyeshadow.jp/commons/images/uploads/2024/05/larry-graham-graham-central-station_higher-ground-712x400.png)
Larry Graham and Graham Central Station – Higher Ground [Stevie Wonder]
![Vampire Weekend – Exit Music (For a Film) [Radiohead]](https://eyeshadow.jp/commons/images/uploads/2024/04/vampire-weekend_exit-music-for-a-film-712x400.png)