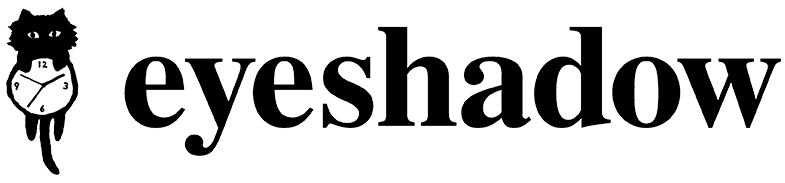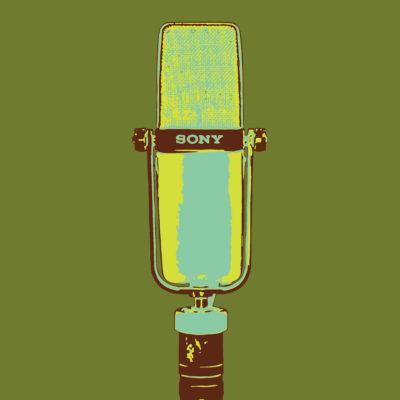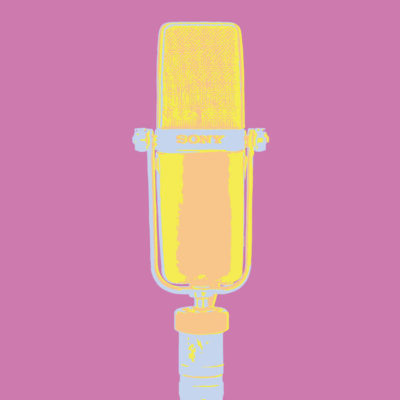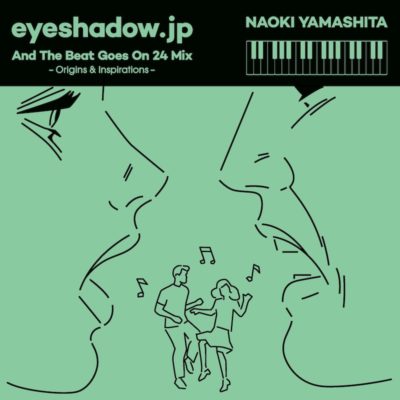鈴木孝弥
Ep.1 / 27 NOV 2019
ブラーの「Pyongyang」を聴くたびに、オレも平壌に行ってみたいという気持ちをかき立てられる。“近くて遠い国”という非建設的なクリシェは、それを国民の脳裏に刷り込むことが目的のプロパガンダであって、その官製の思考停止状態から抜け出したときにひらける風景をいつも想像するのだ。
世界を眺めると、隣国同士の仲が悪く見えるパターンは実に多い。おおかたその不仲関係は、互いに自国民の愛国心を刺激し政情を安定させるための、両国の思惑の一致による古典的な猿芝居であって、韓国との関係を例に挙げるまでもなく、喧嘩するほど仲がいい、というのが真理である。本当に仲が悪くて、退屈な薄っぺらい三文芝居を息を合わせ、手を取り合って熱っぽく、互いに何度政権が変わっても相変わらず脈々と演じ合い続けられるわけがない。
しかしそんな不仲を演出しようにも、同じ台本を共有すること自体ままならないほどに冷え切った関係、という構図も存在する。が、これまた一段高度な外交劇として、両国で推敲に推敲を重ねた極秘のプロット、密約の産物である。互いに互いを“近くて遠い国”とする冷淡な演出を続けることが互いの体制・政府にとって都合がいいなら、万難を排して、つまり自国民がどれだけ心を痛めることになろうとも、そうするだろう。それが政治のための政治だ。
ノルウェーの酔狂なアーティスト、モルテン・トローヴィク(Morten Traavik)が監督し、昨2018年日本公開となったドキュメンタリー映画『北朝鮮をロックした日 ライバッハ・デイ』(原題“Liberation Day”)は、日本の政府、メディア経由ではまず“見させていただけない”北朝鮮の姿が垣間見られる作品だ。ナチス・ドイツを想起させながらファシズムをパロディ化するやり口で反全体主義を標榜する旧ユーゴスラヴィア(現スロヴェニア)のインダストリアル・ロック・バンド、ライバッハが、2015年、北朝鮮の日本による植民地支配からの解放70周年を祝う祖国解放記念日(リベレイション・デイ)に合わせてピョンヤンに招待され歴史的なコンサートを行った。その顛末を記録した映画だが、なぜ外国文化の流入を厳しく規制する“世界一閉ざされた国”が初めて欧米から招いたロック・バンドがこの“ラディカル”なパフォーマンスで名を馳せるアンチ全体主義バンドなのか? さらには世界公開されるこの記録映画の始めの部分には、ライバッハの同胞スラヴォイ・ジジェクが「体制を転覆させる一番の方法は、その価値観を批判することではなく、その裏側を暴露することだ」と語るフッテージまで挿入されているのだから、北朝鮮側は何をどう考えてこの編集をOKしたのか? など、“近くて遠い国”の民として、この映画には興味しか湧かない。
こんな作品が日の目を見た背景には、監督のモルテン・トローヴィクが北朝鮮との間につちかってきた信頼関係がある。トローヴィクは北朝鮮の指導部に取り入って同国でインスタレイションを発表したり、かの国のアーティストたちとの共同制作を重ねたりしてきた。そしてこの映画を撮る前段として、トローヴィクはピョンヤンのエリート音楽学校、クム・ソン音楽学校の生徒たちに自国ノルウェーのグループ、アーハ(a-ha)の(世界的ヒット「Take On Me」を収めた)デビュー・アルバム『Hunting High and Low』を丸々アコーディオンのアンサンブルでカヴァーさせ、ピョンヤン・ゴールド・スターズ名義でアルバム化するプロジェクトも成功させていたのだった。その目玉曲「Take on Me (North Korean Style)」は映画の中でも流れるし、その素晴らしいアルバム『Take On Us』は、CDでリリースされたほか、現在はトローヴィクのウェブサイトで無料配布されている。


Take on Me (North Korean Style)
この映画『北朝鮮をロックした日 ライバッハ・デイ』の内容に対する北朝鮮当局の検閲がどれだけ厳しいものだったとしても、いや、厳しかったなら厳しかっただけ、最終的に我々が観ることのできるシーンが“了”とされている事実の重みは増す。タトゥーを入れ、髪型も服装も“退廃の極み”を呈した珍客たちのそばを離れないDPRKの監視指導員たちや平壌市民たちの無防備で、素朴で、人間味があって、魅力的な姿が彼(女)らの計算づくによる見事な演技によるものだとしたら、彼(女)らとその背後の同国指導部が、さりげなく懐の深さを示す友好的な演技ができる理知的な人々であることを証明している。ならば誰にでもモルテン・トローヴィクの方法であの国と距離を縮めていける望みがあるはずだ。どうせ演技なんだから、不仲を装うよりそちらのプロットで演じ合えばよいだけであり、そもそもライバッハの平壌公演が可能で、日本政府が誠実な態度で話を持っていって日本国を代表する音楽グループであるEXILEや嵐の平壌ライヴを実現させることができない理由はなかろう。
話のついでだが、天皇に奉祝曲を歌うグループがいつも不穏で多分に不敬な名前なのを誰も問題にしないのが不思議でならない。この国には他にいくらでも素晴らしい歌手がいるのに、何故ゆえに敢えて“exile(国外追放、流刑、亡命)”だの“嵐”だの、さざれ石の巌となりて苔のむすまでの国家の安寧と繁栄にはまるで馴染まない、むしろ左翼的、革命的ニュアンスを持つ名のグループに天皇への祝賀の歌を奉じさせるのか? 知性豊かなネトウヨが「天皇は反日左翼」とのたまう意味が少し分かってきた気もするがそれはさておき、それらのグループ名が北朝鮮に好まれないとしたら――この1曲の話で10曲分の紙数を使ってしまいそうなのでもう切り上げるが――ゆかりのあるパパ小泉の引率によるX JAPANの平壌公演を先方に提案してみるのはどうか? これまたリーダーが天皇に曲を捧げたこのグループ名の読みは“バッテン・ジャパン”じゃないよな? という冗談もさておき、もう我々を冴えない政治劇に巻き込まないで、いい加減オレたちに愛すべき隣人と仲良くさせて欲しい。
「Take On Me」なら、イギリスの人気シンガー・ソング・ライター、マット・ヘイルズのソロ・プロジェクト名義アクアラング(Aqualung)がカヴァーし、米ABC系のTVドラマ『グレイズ・アナトミー 恋の解剖学(Grey’s Anatomy)』で使われた静謐なヴァージョンも好きだ。

Take on Me (Grey’s Anatomy Version)
知られた話だが、この“Take on Me”は、アーハが“ぼくにつかまって”、“ぼくに触れて”というノルウェー語の表現”Ta på meg”を逐語的に英単語に置き換え、わざと英文法的に普通じゃないフレイズをひねり出したものだ。それを大胆にも曲名とサビに使用し、英語圏ではその違和感が耳目をひき、結果的にそこが見事にチャームポイントになった。
という曲名も曲名なら、この〈アクアラング〉というのもなかなかに奇抜な芸名ではないか。この言葉から思い浮かべるのは、スキューバ・ダイヴィングの水中呼吸器か、ジェスロ・タル名盤のタイトル(曲)かであろう。実は後者のネイミングも前者から来ているのだが。

Aqualung
アルバムの裏ジャケにはこのアクアラングなる浮浪者の話が載っているが、そのテクストはフォイエルバッハ、マルクス、ニーチェの流れを汲んで、〈初めに人は神を造った〉と始まる。そしてまた、〈人は土の塵でアクアラングを形造った〉ともある。
表題曲で世紀の名曲「Aqualung」の歌詞にあるように、そのアクアラングの名前の由来は、みすぼらしく、孤独で、不潔で、不健康で、絶望したこの浮浪者の呼吸が、深海をダイヴする際の呼吸器の音のようだからであり、彼はそれほどに肺を病んでいる。世界は華やかな運動会やらなにやらには湧き立つ一方で、悲惨なものに対する無関心がはびこり、“人が造った”彼の、そのひどい呼吸さえ、人知れずひっそりと消え入ってゆくのである。アクアラングは人間社会の底辺ならぬ深海でまともな呼吸すら奪われた犠牲者、すなわち人災のメタファーだ。この世のすべては神の思し召しなどでは“ない”。すべては人が造ったものなのだから。
ジェスロ・タルのリーダーのイアン・アンダーソンは、ブルーズ・ロック・サウンドにフルートを導入したことでも知られるが、それはジャズ史上最大の奇才ローランド・カーク(のフルートを吹きながら歌う演奏法)からの影響である。ジェスロ・タル1968年のファースト・アルバム『This Was』から、早速ローランド・カークの「Serenade to a Cuckoo(カッコーのセレナーデ)」をカヴァーしている。

Serenade to a Cuckoo
ジェスロ・タル版「カッコーのセレナーデ」は、フルートと、原曲には使われていないエレクトリック・ギターとの激しい応酬を前面に打ち出したブルーズ・フォーマットのアレンジで、カーク1964年作『I Talk with the Spirits』収録のオリジナル・ヴァージョンとはコード構成も違う。

Serenade to a Cuckoo
オリジナルは、カッコー時計のSEから始まる、おそらくジャズ・ファンで知らない人はいないだろうチャーミングな名演だが、これよりも、1977年のアルバム『Kirkatron』に収録された、75年のモントルー・ジャズ・フェスティヴァルでのライヴ・テイクの方が、テンポが速くグルーヴィかつ一層エキセントリックだ。聴くたびに鳥肌が立つ。

Serenade to a Cuckoo
なので『カーカトロン』のアルバム・オープナーであるライヴ・ヴァージョンの方ばかり聴いていると、勢いで必ずそのまま2曲目の「This Masquerade」も聴いてしまう。もちろんレオン・ラッセルの有名曲、そのインストゥルメンタル・カヴァーだ。アルバムとしては変則的だが、この2曲目はライヴ音源ではなくてスタジオ録音で、この曲のカークはフルートではなくテナー・サックスをしっとり端正に吹きこなしている、という点で1曲目の「カッコー」と目ざましいコントラストを成している。

This Masquerade
で、その「This Masquerade」のヴォーカル版カヴァーなら中本マリのヴァージョンが好きなのだが、それはSpotifyにも上がってないし・・・まあ、世の中的にはジョージ・ベンソン版だろう。76年のアルバム『Breezin’』からのリード・シングルとして切られるとたちまち『ビルボード』でトップ10入りするヒットとなり、このカヴァーで翌年のグラミーを獲った。ジョージ・ベンソンのギタリスト/ヴォーカリストとしてのあらゆる美点を凝縮したようなこの曲は、ラジオ・プレイ用の3分半のシングル・ヴァージョンより、8分のアルバム・ヴァージョンで聴きたい。

This Masquerade
同曲はアルバム『Breezin’』の2曲目に入っているが、1曲目のアルバム・タイトル曲も、言わずと知れたフュージョン/クロスオーヴァー・クラシック。

Breezin’
“最後のソウル・マン”を自称したボビー・ウォマックが、ハンガリーのギタリスト、ガボル・サボー(Gábor Szabó/見慣れた“ガボール・ザボ”の表記は英語式発音に寄せたのかな?)のために作曲した曲のカヴァーだ。そのベンソン・ヴァージョンも「This Masquerade」同様シングル・カットされ、原曲を凌ぐヒットとなった。このベンソン版「Breezin’」大成功の4割はベイシストのフィル・アップチャーチの功績だと思うのだがいかがか? 実は71年のガボル・サボーのオリジナル・ヴァージョンのベイス・ギターもフィル・アップチャーチなんだけどね。この5年間に進んだ“クロスオーヴァー”なサウンドとアレンジの洗練が興味深い。

Breezin’
どうしたことか、この曲はとりわけジャマイカ人にウケがよかったらしく、あの島産の名カヴァーがいくつもある。最も有名なのはボリス・ガーディナー・ハプニング(Boris Gardiner Happening)の73年のアルバム『Is What’s Happening』収録の「Breezin’」だろう。その前72年には、のちにピーター・トッシュのギタリスト、ブジュ・バンタンのバンドのバンマスも務めたマイキー・チャン(Mikey “Mao” Chung)のカヴァーがあり、74年にはこれまた名ギタリストのウィリー・リンド(Willie Lindo)も吹き込んでいる。が、数奇者としては、ダブ・マスター、キング・タビー名義の何やら怪しげなコンピレイション『Jamaican Independence 50th Anniversary』に入っている「Breezing Dub」というヤツに惹かれるのだ。

Breezing Dub
これを初めて聴いたときに2つの??が頭に浮かんだ。
これは本当に故キング・タビーのミックス仕事か?
この元ネタ(ダブのソース)のギター・インストは誰?
少し瞑想して記憶を整理すれば、後者の疑問の糸口は割とすんなり見つかった。何しろ前掲のカヴァー群とは違って、このリディム(伴奏・オケ)はガボル・サボーのアレンジを踏襲せず、ロックステディの名ヴォーカル・グループ、ザ・ヘプトーンズの古典「Fattie Fattie」のリディムを使ってるんだから、聴いたことがあればそのレアさは記憶の奥に残っている。これはカール・ハーヴィ(Carl Harvey)というギタリストの『Ecstasy Of Mankind』という79年のアルバムに入っていたテイクだ。レコードは持っていない(一時探した経験もある。高くて買えなかった)が、検索したらLPまるまるYouTubeに上がっていて、リンク先の19分28秒あたりから元ネタ「Breezing」が聴ける。が、その音源自体すでにインスト曲にダブ処理が施されたもので、YouTubeの写真のクレジットを見るに、キング・タビーのスタジオで弟子のジャミーがリミックスしたものだ。オレ程度の並のレゲエ・オタクにたどり着けるのはここまでで、同テイクでこのミックス以前の音源が存在するのかも分からないし、1つ目の疑問も、「おそらく違う」と感じるが確証はない。
肝心のカール・ハーヴィだが、ヴォーカル・トリオを解消し、トゥーツ・ヒバートとそのバック・バンド、という構成になって以降のトゥーツ&ザ・メイタルズのギタリストである。何度かライヴを観ているからそれは知っている。(つづく)
Cover Triathlon Ep.1 Playlist
1. Pyongyang Gold Stars 「Take on Me (North Korean Style)」
2. Aqualung 「Take on Me (Grey’s Anatomy Version)」
3. Jethro Tull 「Aqualung」
4. Jethro Tull 「Serenade to a Cuckoo」
5. Roland Kirk 「Serenade to a Cuckoo」(alb. 『I Talk with the Spirits』,『Kirkatron (live ver.)』)
6. Rahsaan Roland Kirk 「This Masquerade」
7. George Benson 「This Masquerade」
8. George Benson 「Breezin’」
9. Gábor Szabó 「Breezin’」
10. King Tubby 「Breezing Dub」
Our Covers

Iñigo Pastor

奥山一浩

TOMOE INOUE

Amemiya KSK
EyeTube
![Bobby Hutcherson – The Sailor’s Song [Pages]](https://eyeshadow.jp/commons/images/uploads/2024/04/bobby-hutcherson_the-sailors-song-712x400.png)
Bobby Hutcherson – The Sailor’s Song [Pages]
![Justice Der – Provider [Frank Ocean]](https://eyeshadow.jp/commons/images/uploads/2024/04/justice-der_provider-712x400.png)
Justice Der – Provider [Frank Ocean]
![Taylor Dayne – Tell It to My Heart [Louisa Florio]](https://eyeshadow.jp/commons/images/uploads/2024/04/taylor-dayne_tell-it-to-my-heart-712x400.png)
Taylor Dayne – Tell It to My Heart [Louisa Florio]
![Bananarama – Na Na Hey Hey (Kiss Him Goodbye) [Steam]](https://eyeshadow.jp/commons/images/uploads/2024/04/bananarama_na-na-hey-hey-kiss-him-goodbye-712x400.png)